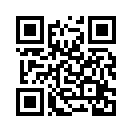2015年03月30日
485系の古い写真
せっかく、イメージモチーフが国鉄時代のスタンプを出したので
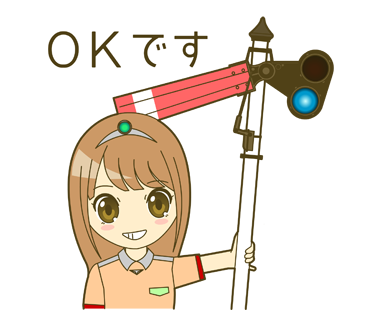
このあたりで、往時を振り返ってみたいと思います。
なおワタシは福岡出身で、二十歳になって東京に出るまで、ずっとそこに住んでいた関係で、撮影場所は主に福岡近辺です。
「宮崎と関係ないじゃん」と思うかもしれませんが、ところがどっこい。当時はまだまだ、福岡-宮崎は鉄道が主役でした。

みなさんご存知、L特急「にちりん」。フチに記された「FUJICOLOR ∞83」という文字が、団塊ジュニア世代には涙モノではないでしょうか(※)。
さすがに、もう食堂車こそありませんが、7両編成というその姿は堂々としていました。
遠くのホームにも485系が停まってます。この当時、博多駅には、長崎・佐世保・熊本・鹿児島・宮崎など、各方面へ走る485系が、ボンネット・貫通型・非貫通型問わずに溢れていて、今のヤング読者から見れば、ヨダレがでるほど羨ましい風景なのかもしれません。
しかし、当時のヤング読者のワタシとしては、「どこへ行っても485系」「どこへ行ってもキハ58」「どこまで行っても415系・475系の顔」であって、特に特急・急行の、あのベージュとクリームの2色は、もはや満腹感しかない状態でした。
もし、当時のワタシが "2015年現在" の博多駅へ行き、様々な特急や九州新幹線を見ると、現在のファンが国鉄時代を目の当たりにするのと同じくらいに興奮しまくることでしょうね。
隣の芝生は永遠に青いものです。
もう一つは、今でも現役のコレ。

713系デビュー時の試乗会です。
昭和59年、1984年ですから、もう30年以上前の話なんですねぇ……
新聞に告知が載って、国鉄へ往復はがきで申し込むという、今から見れば牧歌的なイベントでした。
ちなみに713系は、ご存知の通り、しばらく長崎本線を走ったあと、宮崎へ送り込まれて魔改造され、真っ赤っ赤+レタリング+特急車両の座席装備となり、それでもなぜか「国鉄試作車」の象徴である「900番台」を名乗っていましたが、5年ほど前に「0番台」へ変更され、今ではシングルアームパンタを搭載して、宮崎を走っています。
北九州近郊を走りまくったお古が宮崎へ回ってくる、というのは、今も昔も同じなのですが、現在宮崎の主役となっているCTこと817系に比べて乗り心地はよく、実はこの車両が好きだという人は多いです、はい。
といってもわずか4編成8両しか存在しないので、ほとんど宮崎地区専用モデル、なのです。
(※)注釈は以下の追記に。
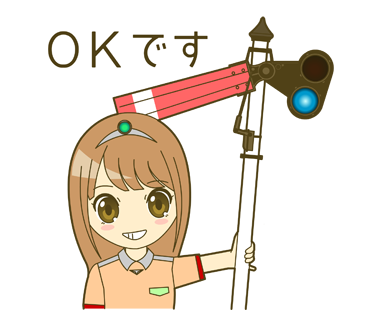
このあたりで、往時を振り返ってみたいと思います。
なおワタシは福岡出身で、二十歳になって東京に出るまで、ずっとそこに住んでいた関係で、撮影場所は主に福岡近辺です。
「宮崎と関係ないじゃん」と思うかもしれませんが、ところがどっこい。当時はまだまだ、福岡-宮崎は鉄道が主役でした。

みなさんご存知、L特急「にちりん」。フチに記された「FUJICOLOR ∞83」という文字が、団塊ジュニア世代には涙モノではないでしょうか(※)。
さすがに、もう食堂車こそありませんが、7両編成というその姿は堂々としていました。
遠くのホームにも485系が停まってます。この当時、博多駅には、長崎・佐世保・熊本・鹿児島・宮崎など、各方面へ走る485系が、ボンネット・貫通型・非貫通型問わずに溢れていて、今のヤング読者から見れば、ヨダレがでるほど羨ましい風景なのかもしれません。
しかし、当時のヤング読者のワタシとしては、「どこへ行っても485系」「どこへ行ってもキハ58」「どこまで行っても415系・475系の顔」であって、特に特急・急行の、あのベージュとクリームの2色は、もはや満腹感しかない状態でした。
もし、当時のワタシが "2015年現在" の博多駅へ行き、様々な特急や九州新幹線を見ると、現在のファンが国鉄時代を目の当たりにするのと同じくらいに興奮しまくることでしょうね。
隣の芝生は永遠に青いものです。
もう一つは、今でも現役のコレ。

713系デビュー時の試乗会です。
昭和59年、1984年ですから、もう30年以上前の話なんですねぇ……
新聞に告知が載って、国鉄へ往復はがきで申し込むという、今から見れば牧歌的なイベントでした。
ちなみに713系は、ご存知の通り、しばらく長崎本線を走ったあと、宮崎へ送り込まれて魔改造され、真っ赤っ赤+レタリング+特急車両の座席装備となり、それでもなぜか「国鉄試作車」の象徴である「900番台」を名乗っていましたが、5年ほど前に「0番台」へ変更され、今ではシングルアームパンタを搭載して、宮崎を走っています。
北九州近郊を走りまくったお古が宮崎へ回ってくる、というのは、今も昔も同じなのですが、現在宮崎の主役となっているCTこと817系に比べて乗り心地はよく、実はこの車両が好きだという人は多いです、はい。
といってもわずか4編成8両しか存在しないので、ほとんど宮崎地区専用モデル、なのです。
(※)注釈は以下の追記に。
FUJICOLOR∞83表記について
昭和50年代後半まで、写真サイズは「Eサイズ」という約11.5cm☓8cmの、白フチありが中心でした。
同時プリント(ネガフィルムの現像と、プリントを同時に行うもの←主に2000年代以降生まれのヤングへ向けた解説)」を注文すると、特別に指定しない限り、コレで仕上げてきました。
フチがあるのは今でこそ斬新ですが、以前は焼きマスクの関係上避けられないもので、これは、2000年前後のインクジェットプリンタでもフチなし写真が「特殊」だったことと、似たような意味合いがあります。
フジカラー(富士フィルム)は、そこに品質の証として、このような表記をしていました。
その後、∞のマークがなかったり、HRフィルム発売に合わせて「FUJICOLOR HR」となったりする等、様々な変遷を遂げ、現在に至……らないですね、はい。ネガプリントはほとんど消えてしまいましたので。
しかし古いアルバムを開くもんじゃありません。全然仕事が進まないです。
ちなみに、なぜ画像の下側ではなく上側に反対向きにプリントされているかというと、ワタシが使っていたカメラがオリンパス・ペンというハーフサイズ(35mmフィルムの1コマに2枚の写真を撮ることができる規格)カメラなので、焼きマスクの関係上そうなったものです。決してカメラを逆さまに構えていたわけではありません。
昭和50年代後半まで、写真サイズは「Eサイズ」という約11.5cm☓8cmの、白フチありが中心でした。
同時プリント(ネガフィルムの現像と、プリントを同時に行うもの←主に2000年代以降生まれのヤングへ向けた解説)」を注文すると、特別に指定しない限り、コレで仕上げてきました。
フチがあるのは今でこそ斬新ですが、以前は焼きマスクの関係上避けられないもので、これは、2000年前後のインクジェットプリンタでもフチなし写真が「特殊」だったことと、似たような意味合いがあります。
フジカラー(富士フィルム)は、そこに品質の証として、このような表記をしていました。
その後、∞のマークがなかったり、HRフィルム発売に合わせて「FUJICOLOR HR」となったりする等、様々な変遷を遂げ、現在に至……らないですね、はい。ネガプリントはほとんど消えてしまいましたので。
しかし古いアルバムを開くもんじゃありません。全然仕事が進まないです。
ちなみに、なぜ画像の下側ではなく上側に反対向きにプリントされているかというと、ワタシが使っていたカメラがオリンパス・ペンというハーフサイズ(35mmフィルムの1コマに2枚の写真を撮ることができる規格)カメラなので、焼きマスクの関係上そうなったものです。決してカメラを逆さまに構えていたわけではありません。
Posted by かるみっこ at 09:53│Comments(0)
│鉄道