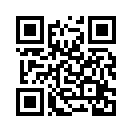› かるブロ › 清武町
› かるブロ › 清武町2013年09月18日
日向沓掛駅ギャラリー
もう25年ほど前。高校2年生の頃。
正月に、「九州一周鉄道の旅」というのを実行しました。
たしか「初夢きっぷ」なるもので、2日か3日間、JR九州の列車が乗り放題というものがありました。
ルートははっきりと覚えていないものの、登場して間もない783系特急「有明」で西鹿児島へ行き、481系ボンネットの「にちりん」で宮崎・小倉経由で博多へ帰り、当時わずかに残っていた夜行急行の一つ、「日南」で宮崎へ向かって、肥薩線経由の急行「えびの」で矢岳などを越えて、博多へ帰るというものでした。
今から考えても、なんだか贅沢な旅ですな。
いや、「乗りっぱなし」という意味では退屈なんですが、新鋭特急あり、レトロあり、急行あり、客車夜行ありで、今となっては体験できないものが多いから、というわけで。
その途中、一か所だけアクシデントがありました。
夜行急行「日南」は、夜に博多を出発し、小倉で方向転換して、大分や延岡を通り、宮崎へ到着すると、そこから普通列車となって各駅に停まりつつ西鹿児島を目指すという、非常にのんびりした列車だったのですが、宮崎駅で降りる予定なのに、うっかり寝過ごしてしまって、気づいたのは清武駅を過ぎた後、だったのです。
あわてて時刻表を見てみると、この次に停まる日向沓掛で折り返しても、次に乗る予定の急行「えびの」には十分に間に合うことが分かったので、とりあえず、その日向沓掛駅で降りることにしました。
宮崎からわずか3駅(当時加納駅はまだなかった)、住宅街の真ん中だろうと思っていたのですが、いざ降りてみると、その名前のごとく、これから鉄路は一路山へ向かう、といわんばかりの雰囲気。ホームも細く、ここで1時間弱を過ごすのも心細いなぁと不安になったものです。
することもないので、寒い中、白い息をはきながらホームの端から端を歩いて時間をつぶすことにしました。白い破線にそって、一歩一歩ゆっくりと歩く。2~3往復したところで、けたたましい列車接近の警報音が鳴って475系の普通列車が到着。暖かい車内でほっと一息ついたもんです。
(実はこの後、用事があって隣の清武駅で一度下車したのですが、それはまた後日にでも)。
日向沓掛こそ、ワタシが宮崎県で初めて降り立った駅なのです。
当時、福岡に住んでいたワタシは、高校生の頃、「どんな進路を選ぶか」「どこに住みたいのか」などとは、まったく考えていませんでした。
漠然と、「東京のような都会に住みたい」とは思っていたものの、それは、まさしく根拠のない夢(=白昼夢)でありました。
それから幾星霜……
まさか、宮崎に移住し、かつ、その日向沓掛駅の最寄りに住むことになるとは。
全く何が起こるか分からない、それが人生というものですね。
そこで今回は、日向沓掛駅をじっくりと紹介したいと思います。

当時ワタシが歩いたホームの破線。恐らく当時のまま、何も変わっていないと思います。ただ、宮崎寄りはホームの嵩上げがなされているので、点字ブロックへ変化しています。
そのホームの都城寄り付近で、ふと右側(国道側)を見上げると、

まるで風立ちぬを彷彿とさせる丘が。この上にパラソルと画板を持って誰かを立たせたいものです。しかし風が吹くと、すぐに鉄道路線へ影響が出るので、やはりやめておきましょう。
いま、まさに山を降りてほっと一息つくという雰囲気のキハ40の2両編成。

電化されているにもかかわらず、普通列車ではディーゼルカーが多いのも、ここの特徴です。
ホーム上の出発信号機。しかしながら、これを見るべき駅員も、車掌もいない……(一部ワンマンじゃないのもある)。

これが戦前生まれの駅であれば、

「米軍の機銃掃射の跡です」などという名物になりそうだけど、いや、ただの穴です。ちなみに日向沓掛駅は昭和40年開業。それまでは、ただの列車の行き違いだけしかできない「信号場」だったとか。

「電話」。といっても公衆電話じゃなくてJRの専用電話。だから開けたりかけたりしちゃいけません。たぶん。
珍客訪問。

風向きによっては、宮崎空港へアプローチする航空機を見ることもできます。なお、駅の南側には宮崎自動車道があり、風景は山間ながらも常にクルマの音がします。
停まらない列車。特急「きりしま」。

現在一眼カメラがぶっ壊れていて、仕方なくIXYをぶら下げて行ったのですが、シャッタースピードなどが設定できないので案の定ブレてます(笑)。
跨線橋。特急も運転されるし、上下で考えると1時間に4~6本は運転されている(はず)なので、安全のためには必要なもんです。

ただしサイズは極小。階段部分は、2人がやっと並べるくらい。
そこに入ると、

なんとなく「オリ」に囲まれているような錯覚。閉所恐怖症にはコワイかもしれません。しかし、それにはちゃんと理由がありまして……

わずか2m程の距離に、20,000Vという高圧電流が流れた裸の線がぶら下がっているのです。図のように、うっかり糸でも垂らそうなら感電死してしまいます。人によっては、ものすごい土砂降りでも感電しちゃう、とか言ってますが、そういう被害を聞いたことはないので、きっと違うんでしょう。しかし、このイラストの子供、本当にヤバいです。まるでtwitterで炎上するバイトテロ写真みたい。

個人的には、跨線橋の上から眺めたこの風景が好き。夜は夜で、ホームの街灯や信号の光が幻想的に見えます。

日本語的には「止れ」(とまれ?)は怪しいけれども、恐らくこれは、かつて跨線橋を使わずに横断していた頃の名残の表記ではないかと思います。ただ、ホーム側に階段などの切り欠きが見当たらないので、職員専用だったのかもしれません。
順番は逆ですが、駅舎内。えっと今回は、「列車でこの駅に途中下車した」というイメージでまとめてます、って終盤になって書くなよ俺と思うのですが申し訳ないです。

右側、どうも出札窓口らしきのがあったんでしょうかね。そして写真に写っていない部分に、トイレがもろに見えていて、あんまり長居したくない雰囲気です。「日向沓掛駅=トイレ」という印象の方も多いと思います。だから駅ノートも置けないです(笑)

遠景で。よくある「日向沓掛駅」の紹介写真です。というか、このカットしか撮れないんですよ、駅前広場がなきに等しいので。

駅前にはロータリーらしきカーブもありますが、これはただの「昇り道」で、この先に自転車置場と、国道から駅につながる道路があります。この坂、雨の日は要注意です。
さきほどの特急の写真のリベンジ。

今回は、シャッター速度が速いのを確認してからの撮影。一見、停車しているように見えますが、本当に通過中です。ええ本当です。と書くとウソっぽいですが、本当です。
この駅に

「ななつ星」が停まることはあるのだろうか………(いやもちろん運転停車で)
正月に、「九州一周鉄道の旅」というのを実行しました。
たしか「初夢きっぷ」なるもので、2日か3日間、JR九州の列車が乗り放題というものがありました。
ルートははっきりと覚えていないものの、登場して間もない783系特急「有明」で西鹿児島へ行き、481系ボンネットの「にちりん」で宮崎・小倉経由で博多へ帰り、当時わずかに残っていた夜行急行の一つ、「日南」で宮崎へ向かって、肥薩線経由の急行「えびの」で矢岳などを越えて、博多へ帰るというものでした。
今から考えても、なんだか贅沢な旅ですな。
いや、「乗りっぱなし」という意味では退屈なんですが、新鋭特急あり、レトロあり、急行あり、客車夜行ありで、今となっては体験できないものが多いから、というわけで。
その途中、一か所だけアクシデントがありました。
夜行急行「日南」は、夜に博多を出発し、小倉で方向転換して、大分や延岡を通り、宮崎へ到着すると、そこから普通列車となって各駅に停まりつつ西鹿児島を目指すという、非常にのんびりした列車だったのですが、宮崎駅で降りる予定なのに、うっかり寝過ごしてしまって、気づいたのは清武駅を過ぎた後、だったのです。
あわてて時刻表を見てみると、この次に停まる日向沓掛で折り返しても、次に乗る予定の急行「えびの」には十分に間に合うことが分かったので、とりあえず、その日向沓掛駅で降りることにしました。
宮崎からわずか3駅(当時加納駅はまだなかった)、住宅街の真ん中だろうと思っていたのですが、いざ降りてみると、その名前のごとく、これから鉄路は一路山へ向かう、といわんばかりの雰囲気。ホームも細く、ここで1時間弱を過ごすのも心細いなぁと不安になったものです。
することもないので、寒い中、白い息をはきながらホームの端から端を歩いて時間をつぶすことにしました。白い破線にそって、一歩一歩ゆっくりと歩く。2~3往復したところで、けたたましい列車接近の警報音が鳴って475系の普通列車が到着。暖かい車内でほっと一息ついたもんです。
(実はこの後、用事があって隣の清武駅で一度下車したのですが、それはまた後日にでも)。
日向沓掛こそ、ワタシが宮崎県で初めて降り立った駅なのです。
当時、福岡に住んでいたワタシは、高校生の頃、「どんな進路を選ぶか」「どこに住みたいのか」などとは、まったく考えていませんでした。
漠然と、「東京のような都会に住みたい」とは思っていたものの、それは、まさしく根拠のない夢(=白昼夢)でありました。
それから幾星霜……
まさか、宮崎に移住し、かつ、その日向沓掛駅の最寄りに住むことになるとは。
全く何が起こるか分からない、それが人生というものですね。
そこで今回は、日向沓掛駅をじっくりと紹介したいと思います。

当時ワタシが歩いたホームの破線。恐らく当時のまま、何も変わっていないと思います。ただ、宮崎寄りはホームの嵩上げがなされているので、点字ブロックへ変化しています。
そのホームの都城寄り付近で、ふと右側(国道側)を見上げると、

まるで風立ちぬを彷彿とさせる丘が。この上にパラソルと画板を持って誰かを立たせたいものです。しかし風が吹くと、すぐに鉄道路線へ影響が出るので、やはりやめておきましょう。
いま、まさに山を降りてほっと一息つくという雰囲気のキハ40の2両編成。

電化されているにもかかわらず、普通列車ではディーゼルカーが多いのも、ここの特徴です。
ホーム上の出発信号機。しかしながら、これを見るべき駅員も、車掌もいない……(一部ワンマンじゃないのもある)。

これが戦前生まれの駅であれば、

「米軍の機銃掃射の跡です」などという名物になりそうだけど、いや、ただの穴です。ちなみに日向沓掛駅は昭和40年開業。それまでは、ただの列車の行き違いだけしかできない「信号場」だったとか。

「電話」。といっても公衆電話じゃなくてJRの専用電話。だから開けたりかけたりしちゃいけません。たぶん。
珍客訪問。

風向きによっては、宮崎空港へアプローチする航空機を見ることもできます。なお、駅の南側には宮崎自動車道があり、風景は山間ながらも常にクルマの音がします。
停まらない列車。特急「きりしま」。

現在一眼カメラがぶっ壊れていて、仕方なくIXYをぶら下げて行ったのですが、シャッタースピードなどが設定できないので案の定ブレてます(笑)。
跨線橋。特急も運転されるし、上下で考えると1時間に4~6本は運転されている(はず)なので、安全のためには必要なもんです。

ただしサイズは極小。階段部分は、2人がやっと並べるくらい。
そこに入ると、

なんとなく「オリ」に囲まれているような錯覚。閉所恐怖症にはコワイかもしれません。しかし、それにはちゃんと理由がありまして……

わずか2m程の距離に、20,000Vという高圧電流が流れた裸の線がぶら下がっているのです。図のように、うっかり糸でも垂らそうなら感電死してしまいます。人によっては、ものすごい土砂降りでも感電しちゃう、とか言ってますが、そういう被害を聞いたことはないので、きっと違うんでしょう。しかし、このイラストの子供、本当にヤバいです。まるでtwitterで炎上するバイトテロ写真みたい。

個人的には、跨線橋の上から眺めたこの風景が好き。夜は夜で、ホームの街灯や信号の光が幻想的に見えます。

日本語的には「止れ」(とまれ?)は怪しいけれども、恐らくこれは、かつて跨線橋を使わずに横断していた頃の名残の表記ではないかと思います。ただ、ホーム側に階段などの切り欠きが見当たらないので、職員専用だったのかもしれません。
順番は逆ですが、駅舎内。えっと今回は、「列車でこの駅に途中下車した」というイメージでまとめてます、って終盤になって書くなよ俺と思うのですが申し訳ないです。

右側、どうも出札窓口らしきのがあったんでしょうかね。そして写真に写っていない部分に、トイレがもろに見えていて、あんまり長居したくない雰囲気です。「日向沓掛駅=トイレ」という印象の方も多いと思います。だから駅ノートも置けないです(笑)

遠景で。よくある「日向沓掛駅」の紹介写真です。というか、このカットしか撮れないんですよ、駅前広場がなきに等しいので。

駅前にはロータリーらしきカーブもありますが、これはただの「昇り道」で、この先に自転車置場と、国道から駅につながる道路があります。この坂、雨の日は要注意です。
さきほどの特急の写真のリベンジ。

今回は、シャッター速度が速いのを確認してからの撮影。一見、停車しているように見えますが、本当に通過中です。ええ本当です。と書くとウソっぽいですが、本当です。
この駅に

「ななつ星」が停まることはあるのだろうか………(いやもちろん運転停車で)
2013年08月31日
清武町の風景 その2

第2回があるのか、本当に危ぶまれた(笑)、清武町のいいね風景です。
個人的なお気に入りは、清武運動公園付近です。
比較的新しく開通した道路です。
大きな地図で見る
まるで高原を走っているかのような錯覚を覚えます。
もちろん、宮崎には「○○原(ばる)」という台地が多いので、そういう場所も高原の雰囲気が満喫できるのですが。

しばし、九州にいることを忘れてしまうような景色。
……だから何だ、と言われればそれまでですが(笑
続きを読む
2013年08月25日
清武町の景色
不定期ではありますが、これから複数回に分けて、清武町のステキな景色を紹介していこうと思います。
まずは、以前から気になっていつつもなかなか訪れられなかった遊歩道のある、大久保付近・庵屋地区。
場所としてはこのあたり。
大きな地図で見る
集落に入った場所なのでわかりづらいですが、クロスモールのある交差点を西へ行く県道13号線に入り、高速をくぐって、比較的新しい交差点を左折して橋を渡り、清武ICへ至る坂道の手前のカーブ付近でちらりと見える細い道がそれです。

竹林に囲まれた、静かな遊歩道が現れます。
素朴な姿の街灯も、より雰囲気を濃くしています。夜間に通るのは躊躇しそうな数しかないですが……。
しばらく昇って振り返ると、

これまたなんともいい雰囲気です。都会であれば、森の公園の遊歩道として週末あたりに人気の出そうなスポットです。
ただ、清武では、近所の小学校の通学ルートで使われているにすぎないようですが……。
それを象徴するかのごとく、この階段を登りつめると

なんだか昭和なイメージの看板が現れ、車道に直角でぶつかり、終了。
さきほどの、庵屋地区「通学ルート」は、この遊歩道を階段で昇り、しばし丘陵の上部付近を歩いたあと、次は集落と集落をつなぐ下り坂を降りて、再び小学校への坂を昇るという、いささかアップダウンの激しい通学路となっております。
もう一つは、同じ大久保地区にある「大久保学習センター」。
大きな地図で見る
ここのグラウンドにあるいちょうの木が印象的です。

秋になると、子供たちが葉を集めて遊ぶそうです……。なかなか楽しそうですね。
まずは、以前から気になっていつつもなかなか訪れられなかった遊歩道のある、大久保付近・庵屋地区。
場所としてはこのあたり。
大きな地図で見る
集落に入った場所なのでわかりづらいですが、クロスモールのある交差点を西へ行く県道13号線に入り、高速をくぐって、比較的新しい交差点を左折して橋を渡り、清武ICへ至る坂道の手前のカーブ付近でちらりと見える細い道がそれです。

竹林に囲まれた、静かな遊歩道が現れます。
素朴な姿の街灯も、より雰囲気を濃くしています。夜間に通るのは躊躇しそうな数しかないですが……。
しばらく昇って振り返ると、

これまたなんともいい雰囲気です。都会であれば、森の公園の遊歩道として週末あたりに人気の出そうなスポットです。
ただ、清武では、近所の小学校の通学ルートで使われているにすぎないようですが……。
それを象徴するかのごとく、この階段を登りつめると

なんだか昭和なイメージの看板が現れ、車道に直角でぶつかり、終了。
さきほどの、庵屋地区「通学ルート」は、この遊歩道を階段で昇り、しばし丘陵の上部付近を歩いたあと、次は集落と集落をつなぐ下り坂を降りて、再び小学校への坂を昇るという、いささかアップダウンの激しい通学路となっております。
もう一つは、同じ大久保地区にある「大久保学習センター」。
大きな地図で見る
ここのグラウンドにあるいちょうの木が印象的です。

秋になると、子供たちが葉を集めて遊ぶそうです……。なかなか楽しそうですね。