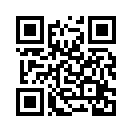2015年11月15日
編成美
"編成美"という言葉がある。主に鉄道用語として用いられる。
鉄道車両は、種別や動力手段によって雑多な種類があるが、すくなくとも同じ型式であれば、外観のデザインや、車体の高さなどは同じである。
それが、十数両の長さになると、大蛇のように長い連続体となり、存在感を増す。
直線で眺めても美しいが、カーブなど特殊な環境であれば、その連続したスタイルが更に多様な表情を表し、なおのこと美しく感じる。
都心部における通勤電車や、新幹線などでは、この"編成美"がしっかりと守られているものの、地方においては、残念ながらすでに過去のものとなってしまっているようだ。
九州で恐らく最後にそれを感じたのは、787系「つばめ」ではなかろうかと思う。885系や883系でもそれなりに長い編成なので、同じものを感じるはずなのだが、787系に比べてインパクトが弱い。恐らく、同型式のもつ、濃いグレーの塗装がその存在感を一層高めているのであろう。
しかし787系も九州新幹線全通とともに主役の座を追われ、昔日の面影が薄い。
国鉄時代はどうだったか。
かつて「ミニ特急」と言われその名をとどろかせた、博多-佐世保間の「みどり」も、それ単体では4両編成だった。当時は驚きの短さだったのに、現代の地方であれば違和感のない存在だ。しかしこの「みどり」、博多-肥前山口間は「かもめ」(8両編成)と併結していたから、堂々12両の特急電車であった。
その後、「かもめ」と「みどり」は、博多-佐賀(付近)の頻発運転、いわゆるフリークェントシー重視のダイヤ実現のために分離されたり、再び併結されたり、「ハウステンボス」が間に挟まるなど、紆余曲折を経て現在に至るのはご存知の通りだ。
なお、「かもめ」には、一時期、編成美を崩す車両が混じることもあった。

写真をご覧いただくと、先頭車両だけがいくぶん車体の高さが低いのがお分かりかと思う。どことなくこの間抜けな、崩された"編成美"は、上越線特急「とき」の廃止で余った181系先頭車を九州に異動させるという強引さで誕生したものだった。JR分社時代の今では考えられない、おおらかな転属劇が、このころはよく行われていた。
編成美といえば思い出すのは、当然のことながらブルートレインである。

毎日、東海道から山陽路を、青い車両を連ねた列車が、何本も何本も走っていく。
しかし、ついに需要減には耐えられず、全廃されてしまったのは記憶に新しい。
と、ここで、果たして将来的に、新幹線や通勤電車以外で、こういった"編成美"を眺めることができるのか、という疑問に当たってしまった。
出発駅から目的駅まで、同一の車両を、十数両もつないで走る必要性があるのか、ということだ。
残念ながら、ポジティブな意見は思い浮かばない。
もし、今からそう遠くない将来、化石燃料が枯渇して、自動車は燃料切れで動けず、飛行機も空を飛べないとしたら、必然的に電気でも動ける鉄道が脚光を浴びるのは間違いないだろう。
そうなると、長距離を移動する客が再び鉄道へ回帰し、"編成美"を再現することになるのではないか。
いや、それはつまり今の新幹線と同じだ。
もう少し時代が進み、電気自動車&自動運転が現実になれば、高速道路上では同じ目的地へ行くクルマが、お互いに連結されて走るに違いない。その方が事故も減るし渋滞も少なくなる。
Back to the Future2では、2015年にクルマが空を飛ぶと言ってたが実現していない。
それほど将来を予測するのは難しい。
ちなみに、なぜか、新幹線に対して、私は編成美を感じることが少ない。
なぜだろうか、どうしてだろうかといろいろと考えてみたいのだが、たぶん、これではないだろうかという結論を見出した。
新幹線は、カーブが少ないのだ。
だから、車体をうねうねとさせる場面がない。
これが編成美を遠ざけている原因かもしれない、と、半分眠りかけた頭で考えております。

鉄道車両は、種別や動力手段によって雑多な種類があるが、すくなくとも同じ型式であれば、外観のデザインや、車体の高さなどは同じである。
それが、十数両の長さになると、大蛇のように長い連続体となり、存在感を増す。
直線で眺めても美しいが、カーブなど特殊な環境であれば、その連続したスタイルが更に多様な表情を表し、なおのこと美しく感じる。
都心部における通勤電車や、新幹線などでは、この"編成美"がしっかりと守られているものの、地方においては、残念ながらすでに過去のものとなってしまっているようだ。
九州で恐らく最後にそれを感じたのは、787系「つばめ」ではなかろうかと思う。885系や883系でもそれなりに長い編成なので、同じものを感じるはずなのだが、787系に比べてインパクトが弱い。恐らく、同型式のもつ、濃いグレーの塗装がその存在感を一層高めているのであろう。
しかし787系も九州新幹線全通とともに主役の座を追われ、昔日の面影が薄い。
国鉄時代はどうだったか。
かつて「ミニ特急」と言われその名をとどろかせた、博多-佐世保間の「みどり」も、それ単体では4両編成だった。当時は驚きの短さだったのに、現代の地方であれば違和感のない存在だ。しかしこの「みどり」、博多-肥前山口間は「かもめ」(8両編成)と併結していたから、堂々12両の特急電車であった。
その後、「かもめ」と「みどり」は、博多-佐賀(付近)の頻発運転、いわゆるフリークェントシー重視のダイヤ実現のために分離されたり、再び併結されたり、「ハウステンボス」が間に挟まるなど、紆余曲折を経て現在に至るのはご存知の通りだ。
なお、「かもめ」には、一時期、編成美を崩す車両が混じることもあった。

写真をご覧いただくと、先頭車両だけがいくぶん車体の高さが低いのがお分かりかと思う。どことなくこの間抜けな、崩された"編成美"は、上越線特急「とき」の廃止で余った181系先頭車を九州に異動させるという強引さで誕生したものだった。JR分社時代の今では考えられない、おおらかな転属劇が、このころはよく行われていた。
編成美といえば思い出すのは、当然のことながらブルートレインである。

毎日、東海道から山陽路を、青い車両を連ねた列車が、何本も何本も走っていく。
しかし、ついに需要減には耐えられず、全廃されてしまったのは記憶に新しい。
と、ここで、果たして将来的に、新幹線や通勤電車以外で、こういった"編成美"を眺めることができるのか、という疑問に当たってしまった。
出発駅から目的駅まで、同一の車両を、十数両もつないで走る必要性があるのか、ということだ。
残念ながら、ポジティブな意見は思い浮かばない。
もし、今からそう遠くない将来、化石燃料が枯渇して、自動車は燃料切れで動けず、飛行機も空を飛べないとしたら、必然的に電気でも動ける鉄道が脚光を浴びるのは間違いないだろう。
そうなると、長距離を移動する客が再び鉄道へ回帰し、"編成美"を再現することになるのではないか。
いや、それはつまり今の新幹線と同じだ。
もう少し時代が進み、電気自動車&自動運転が現実になれば、高速道路上では同じ目的地へ行くクルマが、お互いに連結されて走るに違いない。その方が事故も減るし渋滞も少なくなる。
Back to the Future2では、2015年にクルマが空を飛ぶと言ってたが実現していない。
それほど将来を予測するのは難しい。
ちなみに、なぜか、新幹線に対して、私は編成美を感じることが少ない。
なぜだろうか、どうしてだろうかといろいろと考えてみたいのだが、たぶん、これではないだろうかという結論を見出した。
新幹線は、カーブが少ないのだ。
だから、車体をうねうねとさせる場面がない。
これが編成美を遠ざけている原因かもしれない、と、半分眠りかけた頭で考えております。