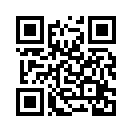› かるブロ › 2015年11月19日
› かるブロ › 2015年11月19日2015年11月19日
無人駅を訪れて
鉄道での旅では、駅を抜きに語ることはできない。
それは列車が必ず駅で乗降を取り扱うから、という理由ではあるが、それ以上に、駅舎やホーム、付帯設備など、少なくとも個人の一戸建てよりも多くの建造物がそこに存在し、旅人を出迎えてくれるからだと、個人的に思う。
例えば路線バスの旅で、バス停そのものが主役になることはまずない。せいぜい、川南町の「トロントロン」バス停のように、特殊な名称を持つものであれば話題になる可能性があるという程度で、そういったものでもただ看板にペンキで文字が書かれている程度であって、これはという設備がないから、どうにも扱いづらい。
以前、「駅もそのうち、バス停のようになるのではないか」と懸念を込めて書いたのは、そういった魅力の低下であり、それが続くと、鉄道を使った旅そのものも減ってしまう気がする。そうなるとひたすら残念である。
さて現状では、とりあえずまだまだ駅は元気であり、無人化しながらも、設備はそのまま残っているところが多い。

夜の駅というのは非常にムードが高いと思う。いかにも「今から旅立ちます」という印象に包まれている。もし私が女性ならば、夜の駅で口説かれたら十中八九落ちてしまうだろう。しかし残念ながら中年男性であるし、しかも夜の駅から旅立つ夜行列車も、もはや存在しない。ただ、町から帰ってくる通勤通学客を待つだけになっている。
青島駅といえば、以前は交換待ちの際に「ういろう」売りのおばさんが現れ、プチ車内販売を行うこともあった。いつしかその姿もなくなり、静まり返っている。
利用客の多い駅は、その増加とともに利便性を高めるべく改良され、進化していく。博多駅などはその代表格で、そもそも平屋だった駅が、九州の中心として君臨するためにルネサンス調の駅舎へ変わり、客数が増えたのと都市化が進んで郊外へ移転すると同時にデパート併設の駅ビルとなる。そしてさらに後年、魅力を高めるため、新たな駅ビルを建設した。
また、利用客の少ない駅であれば、早々に駅舎をたたんで簡素化するのだが、肥薩線のように、そのどちらとも行われず、明治時代の古き良き姿を保っている。

かつて写真とか模型でしか見たことのない、「急行停車駅」のつくりで、木造駅舎、広い待合室、出札窓口、手荷物用窓口、木製の改札、壁に作りつけられたベンチ、そして団体用の改札など、これらがそのまま残っている。高度成長期に駅舎が建て替えられる例が多かったのだが、あまりにも利用客が少なかったから、そのまま存置されたのだろうと思う。
また、建て替えられた例として、非常に簡素なスタイルになった駅もある。

主に九州では、木造駅舎は白蟻被害を受けることから、シンプルなパネル構造の待合所があるだけで、出札窓口などはもとより設けずに済ませてしまう例も多い(ただし、大隈夏井駅には、小さいながらもきっぷうりば跡地のような窓がある)。これはこれで斬新なスタイルだが、居心地がいいとは決して言えない。駅舎がないよりもまし、という程度だろうか。
もし今、鉄道路線が新たに建設され、経済性を重視して合理的に駅をつくるのであれば、みんな同じ顔ぶれになるはずだ。それはそれで一理あるのだが、やはり物足りない。しかし、長い歴史を持つ路線であればあるほど、そこに存在する駅は、上記のような紆余曲折を経て、多様な顔を持つ。これがまた、鉄道で旅をする魅力であろうと思う。

それは列車が必ず駅で乗降を取り扱うから、という理由ではあるが、それ以上に、駅舎やホーム、付帯設備など、少なくとも個人の一戸建てよりも多くの建造物がそこに存在し、旅人を出迎えてくれるからだと、個人的に思う。
例えば路線バスの旅で、バス停そのものが主役になることはまずない。せいぜい、川南町の「トロントロン」バス停のように、特殊な名称を持つものであれば話題になる可能性があるという程度で、そういったものでもただ看板にペンキで文字が書かれている程度であって、これはという設備がないから、どうにも扱いづらい。
以前、「駅もそのうち、バス停のようになるのではないか」と懸念を込めて書いたのは、そういった魅力の低下であり、それが続くと、鉄道を使った旅そのものも減ってしまう気がする。そうなるとひたすら残念である。
さて現状では、とりあえずまだまだ駅は元気であり、無人化しながらも、設備はそのまま残っているところが多い。

夜の駅というのは非常にムードが高いと思う。いかにも「今から旅立ちます」という印象に包まれている。もし私が女性ならば、夜の駅で口説かれたら十中八九落ちてしまうだろう。しかし残念ながら中年男性であるし、しかも夜の駅から旅立つ夜行列車も、もはや存在しない。ただ、町から帰ってくる通勤通学客を待つだけになっている。
青島駅といえば、以前は交換待ちの際に「ういろう」売りのおばさんが現れ、プチ車内販売を行うこともあった。いつしかその姿もなくなり、静まり返っている。
利用客の多い駅は、その増加とともに利便性を高めるべく改良され、進化していく。博多駅などはその代表格で、そもそも平屋だった駅が、九州の中心として君臨するためにルネサンス調の駅舎へ変わり、客数が増えたのと都市化が進んで郊外へ移転すると同時にデパート併設の駅ビルとなる。そしてさらに後年、魅力を高めるため、新たな駅ビルを建設した。
また、利用客の少ない駅であれば、早々に駅舎をたたんで簡素化するのだが、肥薩線のように、そのどちらとも行われず、明治時代の古き良き姿を保っている。

かつて写真とか模型でしか見たことのない、「急行停車駅」のつくりで、木造駅舎、広い待合室、出札窓口、手荷物用窓口、木製の改札、壁に作りつけられたベンチ、そして団体用の改札など、これらがそのまま残っている。高度成長期に駅舎が建て替えられる例が多かったのだが、あまりにも利用客が少なかったから、そのまま存置されたのだろうと思う。
また、建て替えられた例として、非常に簡素なスタイルになった駅もある。

主に九州では、木造駅舎は白蟻被害を受けることから、シンプルなパネル構造の待合所があるだけで、出札窓口などはもとより設けずに済ませてしまう例も多い(ただし、大隈夏井駅には、小さいながらもきっぷうりば跡地のような窓がある)。これはこれで斬新なスタイルだが、居心地がいいとは決して言えない。駅舎がないよりもまし、という程度だろうか。
もし今、鉄道路線が新たに建設され、経済性を重視して合理的に駅をつくるのであれば、みんな同じ顔ぶれになるはずだ。それはそれで一理あるのだが、やはり物足りない。しかし、長い歴史を持つ路線であればあるほど、そこに存在する駅は、上記のような紆余曲折を経て、多様な顔を持つ。これがまた、鉄道で旅をする魅力であろうと思う。